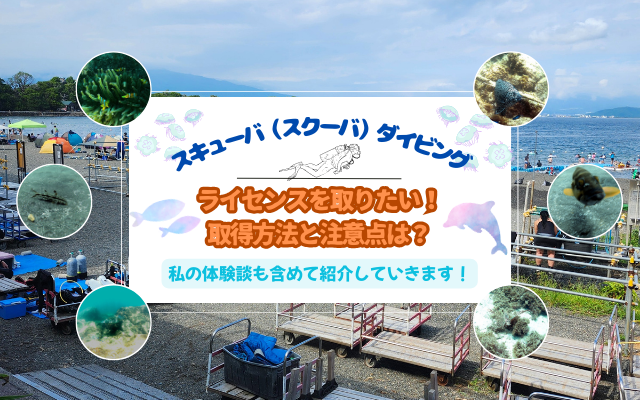「ダイビングを始めたいけど、ライセンスはどこで取ったらいいの?」
「ダイビングライセンスってどこも一緒なの?」
「ダイビングライセンスを取得するのに、注意するところは?」
 なつ
なつ今回は、上記のような質問について解説していきます!
皆さん、ダイビングの経験はありますか?
スキューバ(スクーバ)ダイビングをやってみたい、ライセンスを取りたいと思ったことはありますか?
体験ダイビングを開催しているショップに行けば、たくさんの魚や海の中の景色など様々な体験や観察ができますよね。
そんなスキューバ(スクーバ)ダイビングですが、、、
未経験でも興味がある方や体験ダイビングをして、もっともっと潜りたいと思う方!
ダイビングライセンスについて気になるところだと思います。
そこで、私の経験も踏まえ、今回はライセンスについてやショップの選び方など解説していきます。



Let’s Go!(^^)!
- ショップから選ぶのがおすすめ
- Cカードが国内の他の店舗で使えるか、海外で使えるかを確認すること
ダイビングライセンスとは?


前述したとおり、スキューバ(スクーバ)ダイビングは、ライセンスがなくても体験できちゃいます!
じゃあ、わざわざライセンスなんてとらなくてもいいじゃん、、、( 一一)
そうです、取らなくてもいいんです!
では何のために取得するのか、、、
それは、海の基本を知り、機材の使い方やダイビングのルール、緊急時の対応など学びます。
そして、ダイビングできるポイント(場所)が多くなり、体験ダイビングでは行けない深度に行ったり、カメラやスケッチの技術の向上やその他の海の楽しみ方を教えてもらったり!
ライセンスを取得することで、出来ることや場所がかなり広がります!
深度が少し深いだけでも、見られる魚や環境が全く違うので、今まで以上の発見があります。
では、Cカードやライセンスの種類など詳しく解説していきます!



同じダイバーなのに、みんなそれぞれ楽しみ方が違う( ´∀` )
ダイバー同士で話すととっても面白いですよ(⌒∇⌒)
Cカードとは?


ダイビングを本格的にやりたいと思ったら、Cカードの取得はした方がいいです。
でも、Cカードってそもそも何なのか、いまいちわからない方もいるかと思います。
そこで、まずはCカードについて紹介していきます。
Cカードは、ダイビングに必要なスキルや知識を習得したことを証明するものです。
そのため、ライセンスと言っていますが、国に認められた資格(免許)ではありません。潜水士とは全く違うライセンスとなります。
ちなみに、潜水士の資格だけ持っていても、ダイビングは体験までしかできません。
本格的なダイビングをするなら、Cカードは必ず必要になります。
Cカードの取得後も、いろんな種類のCカードを取得できます。
ランクを上げることで、潜れる範囲も広くなります。



ダイバーとして成長を目指すきっかけにもなりますね(^^♪
ダイビングの指導団体について


ダイビングスクールは、必ずどこかしらの民間指導団体に所属しています。
その民間団体(指導団体)は、約40ほどあるといわれます。
それぞれの民間団体(指導団体)には、プログラムや理念など少しずつ違います。
そこで、一番気をつけることは「世界で共通して使用できるCカード」なのか「取得した国のみ、取得したショップのみ使用できるCカード」なのかです。
日本で知られている一般的な指導団体は、PADI(パディ)、NAUI(ナウイ)、BSAC(ビーエスエーシー)、SSI(エスエスアイ)、SNSI(エスエヌエスアイ)、CMAS(クマス、シーマス)です。
その中で、一番知られているのが「PADI」という民間団体です。
なんといっても、ダイバー教育のプログラムが充実しており、知識も技術もしっかりと手厚く教育されます。そのため、世界からの信頼度も高いです。



各指導団体には、ダイバーランクがあるので、ダイバーになった後も、目標を持てます(⌒∇⌒)
ライセンスの種類(オープンウォーター・アドバンスなど)


前述でも、軽く述べていますがライセンスもランクがあります。
しかし、細かく説明すると分かりにくくて、長くなってしまうのでなるべく簡潔に説明しようと思います。



指導団体が違っても、基礎は大体同じなので参考にしてください!(^^)!
PSD(スクーバダイバー)
最短2日で取得可能。最大深度12mでプロダイバーの引率が必要。
飛び級できるので、飛ばすことがほとんど!
OWD(オープンウォーターダイバー)
最短3日で取得可能。最大深度18mでバディー潜行可能。
(最初は、このランクで海を楽しんでいる方が多いです。)
最短1日で取得可能。
アドベンチャー・イン・ダイビング・プログラムの項目の中から、自分の興味があるダイブスキルを3つ選び、スキルアップができる。
ディープ・ダイビングを選択すると、最大深度が30mまでになる。
最短2日で所得可能。最大深度は30m。
アドベンチャー・イン・ダイビング・プログラムの項目の中から、水中ナビゲーションとディープ・ダイブに加え3種類興味あるアドベンチャー・ダイブを選択。
日本全国のダイビングスポットだけでなく、世界中のダイビングスポットを存分に楽しめる。
RED(レスキュー・ダイバー)
最短3日で取得可能。
REDは、セルフレスキュースキルを向上し、トラブルを未然に防ぐ知識や技術をはじめ、トラブルに対応する知識や技術を身に付ける。
EFRは、陸上で起きる心肺停止など生命にかかわる緊急時のケア(一次ケア)や生命にかかわらないけがや病気のケア(二次ケア)の知識と技術を身に付ける。
AED(自動体外式除細動器)や、純酸素キッドの使用も練習する。
大まかにまとめると、このような感じです。
一般のダイバーとして楽しむなら、レスキューダイバーまであるとよいといわれています。
その理由としては、自分の安全を守ることやトラブルに対しての対応力が違ってくるからです。
レスキューダイバーの次は、ダイブマスターで、インストラクターを目指したい方やインストラクターと同じくらいの知識を持ちたい方は、この先のランクも調べてみてください(^▽^)/



もっともっと、内容としては細かくあるので、興味がある方は調べてみてくださいね( *´艸`)
取得するメリット・活かせる場面


皆さんは、ダイビングの経験はありますか?
私は、ダイビングの経験なしでライセンスを取得しました。
そのため、ライセンスなしでのダイビングの経験がありません。
大体の方は、ダイビングの経験し楽しさを知って、もっとダイビングをしたいと思った方がライセンスの取得を考えると思います。
しかし、ダイビング自体はライセンスなしでもできるので、悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで、前述でも少し話していますが、ライセンスを取得することのメリットや、活かせる場面について紹介していきます。
ライセンスを取得することのメリット
- 潜行可能な推進が深くなる
- ダイビングできるスポットの選択肢が増える
- ダイビングで行ける範囲が広くなる(洞窟や沈船ダイビングなど)
- インストラクターなしでも、潜行可能になる
- 自分で泳ぎ、見て撮ってスケッチして、、、自分の楽しみ方ができる
ライセンスを取得することのデメリット
- 勉強やトレーニング期間が必要
- それなりの出費がある
いかがですか?
メリットを紹介しつつ、デメリットも紹介していきました。
やはり、ライセンス取得の一番のメリットは行動範囲が広くなることですよね。
私も、ダイビングをして初めて知りましたが、少し深度が変わるだけで、見られる魚や景色は違います。
行動範囲が広くなると、新しい発見がたくさんあって、どんどん楽しくなります。



深度が深いとちょっと怖い(;^ω^)
そんな時、、、私は、インストラクターの方を見て、深呼吸して落ち着いています(⌒∇⌒)
ライセンスを活かせる場面
- ダイビングショップでボンベ/タンクを借りられる
- 世界中でダイビングできる
- 1度取得したら、永久的なのでいつでもダイビングできる
Cカードは、ダイビングをするためには必要なライセンスとなります。
ダイビングをするためのボンベ / タンクを借りるのにもCカードが必要なので、ダイバーは皆持ち歩いています。
そして、自分が団体から認めまれたダイバーであるという証明にもなるので、必ずケータイする必要があります。
世界で認められた団体のCカードを取得していれば、世界中の海をダイビングで楽しめます。



世界と聞くと、夢が広がる気がします( ´∀` )
私はいつか、ガラパゴス諸島(エクアドル)でたくさんの魚とアシカとダイビングを楽しみたい(^_-)-☆
ダイビングライセンスはどこで取れる?主な選択肢は?


ダイビングのライセンスってどこで取れるのかよく知らない方も多いのではないでしょうか。
私は、沖縄や伊豆など観光地に行かなと取れないと思っていました。
そんなこともありません!
ショップ自体は、多かれ少なかれ北海道から沖縄まであります。
また、海外旅行・国内旅行がてらライセンスを取得することを考えている方も多いかもしれません。
そこで、それぞれのライセンスの取得方法のメリット・デメリットを詳しく紹介していきます。



ライセンスはどこでも取得可能‼
でも、ライセンス取得後も、ダイビングを楽しめるようにしましょうね(^▽^)/
国内 vs 海外(それぞれのメリット・デメリット)


ダイビングのライセンスを旅行がてら取得したいと思っている方もいらっしゃると思います。
また、海外でライセンスの取得をしたいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
どちらにせよ、海外でも国内でもライセンスの取得は可能ですが、それなりのメリットやデメリットがあります。
そんな国内と海外でのライセンス取得のメリット・デメリットをまとめてみたので参考にしてみてください。
国内
メリット
- 普段の休日を利用してライセンスを取得できる
- 海外で取るより安く済む
- どこのショップも日本語なので安心
- 自宅から通いやすい距離にショップがある場合、ダイビングを続けやすい
- 都市型を利用する場合、顔見知りのインストラクターと一緒にダイビングするため安心
デメリット
- ツアーや都市型でライセンスを取得すると、料金が高くなる
- 場所によっては、大人数でライセンスを取得する必要がある
以上が、国内編です。
都市型とリゾート型で少し、考え方やメリット・デメリットも違ってきますが、大まかにまとめると上記のような感じです。
次は、海外編を紹介します。
海外
メリット
- 短期集中でライセンスが取得できる(学科はオンラインが多い)
- 日本では会えない生き物たちと会える可能性がある
デメリット
- 悪天候や体調不良、トラブルなどでライセンスが取得できずに終了することがある
- 余裕を持った日程調整が必要
- ダイビングライセンスの講習を受けているときは、観光は難しい
- 旅行がてらとはいえ、国内でライセンスを取るより費用は高額
- 言語が英語が多いため、理解不十分になる可能性あり。
(重大事故にもつながるので英語に相当な自信がなければ危険。) - 帰国後、ペーパーダイバーになりがち
いかがですか?
やはり、海外なだけあってデメリットも多くなってしまいます、、、
しかし、日本では経験できないことも経験しながら、ライセンスを取得できるのは海外の特権ですよね!
海外でライセンス取得後は、帰国後速やかに自分に合ったショップを探すこと!
そうすれば、ペーパーにならず、せっかく取得したライセンスも活かすことができます!



どちらも、メリットとデメリットがあるので、自分に合ったライセンスの取得方法を見つけてくださいね(^_-)-☆
都市型スクール vs リゾート型スクール


どこでもライセンスは取得できる!と言われても、実際どこで取ればいいのがベストなのか、、、
せっかくのライセンス取得で、悩まれる方は多いと思います。
実際、ショップがすぐ決まる方は、もともとダイビングをしている知り合いの紹介が多いです。
また、リゾート型なら旅行会社のツアーでもともと組まれているショップやネットなどで見つける方が多いと思います。
そこで、リゾート型と都市型のメリット・デメリットをまとめて紹介していきます。
リゾート型
メリット
- 旅行期間中のライセンス取得のため、短期集中型
- ダイビングスポットに近いショップのため、周辺のダイビングスポットに関して知識や経験が豊富
- 都市型より料金が安い
デメリット
- 天候や体調によっては、ライセンスを取得できないまま終了する可能性がある
- 下見や説明会など参加できないことが多い
- シーズン中は、人数が多いために大人数での講習となる可能性がある
- 旅行のため、飛行機や電車など交通機関の料金や宿泊費用は別
- ライセンス取得後ペーパーダイバーになりやすい
都市型
メリット
- ライセンス取得後も、インストラクターは同じ方の可能性が高い
- インストラクターの方々を、よく知るため誰がインストラクターになっても安心
- ダイビング以外にも定期的な食事会や飲み会などがある
- ショップのお客さんと仲良くなる機会が多い
- 機材購入時は、よく知っているインストラクター(ショップ)から買えるため安心
- 仕事の合間や普段の休日を利用してライセンスが取れる
デメリット
- リゾート型より高い
- 移動時間が長い
- 一部のショップでは、機材の押し売りがある
- ショップによっては、ダイビングをするときは大人数
- ダイビングツアーやファンダイビングの開催が少ない
いかがですか?
リゾート型も都市型もそれぞれ特徴があり、メリット・デメリットがありますね!
これらを、踏まえて自分達に合ったライセンスの取得方法を検討してみてください(^∇^)



自分のペースで確実にライセンスを取りたいなら、都市型がおすすめ(^^)
後悔しないショップの選び方


ショップの種類やライセンスの取得方法など、いろいろ説明してきましたが、結局ショップの選び方はどうなのか、、、
特に、都市型でライセンスを取得すると長く付き合うショップとなる可能性が高いです。
しかし、行ってみて初めて思っていたのと違ったり、人間関係にストレスを感じてしまったり、、、なるべく避けたいことですよね。
もちろん、ショップを新しく見つけて、ダイビングを楽しく続けていくことも可能です。
でも、なるべくならライセンスを取ったところで長く付き合う方がいいに越したことはありません。
なんせ、自分の苦手なことや性格、泳ぎ方や楽しみ方など分かってくれているので、自分としても楽にダイビングができます。
そこで、ショップを決めるときの注目点をまとめてみたので参考にしてください!



なるべくなら、通う前にショップに行って話を聞いたり、体験ダイビングで直接インストラクターの対応などを体験してみるのも◎❢
①座学講習スタイル(通学・オンライン併用など)


ライセンスを取得するのに、座学講習が含まれています。
その座学講習ですが、受講方法が主に2種類!
- eラーニング(オンラインでの受講)
- インストラクターによる直接の受講
eラーニング受講は、決められた日にちまでに自分で進めていくスタイル。
リゾート型でライセンスを取得する方はほとんどこちらです。
仕事や学校の合間に気軽にできるので、手軽でいいですが、計画的に進めないと大変なことに、、、
そして、直接受講ですが、こちらはショップに直接行き、インストラクターから直接教えてもらいます。
ショップに直接行く手間や時間を作る必要がありますが、分からないところやテストで間違ってしまった所をすぐに聞いたり、振り返ったりできるのがいいですね。
また、インストラクターの方の体験や実際を直接聞けるのもいいところです。
座学は大変で、めんどくさいかもですが、、、
直接、実践にもつながることもありますし、なんといっても自分の命や他人の命を守るための講習内容でとっても大切!
しっかりと、自分が受講できるスタイルで受けましょう!



PADIしか分かりませんが、硬い座学ではなく、ほとんど動画だったので楽しかったです(^▽^)/
②インストラクターの質・実績を確認する


なんといっても、ここは重要ですよね。
インストラクターにも、ランクがありそれぞれ経験値も違います。
特に、最高ランクであるコースディレクターがいるショップだと安心です。
そして、実績なども確認が必要ですね。
もちろん、経験があればあるほどいいですし、そこのショップでの事故の有無なども重要となります。
そして、PADIではCカードが2種類あります。
通常のカードとゴールドカードです。
特に、何が違うとかはありません。
しかし、ゴールドカードが発行できるのは、「教育」、「地域活動への参加」、「環境保護活動」「体験」「機材」などPADIから認められているショップである証明です。



他のダイバーライセンスも考えている方は、コースディレクターがいるショップだとショップを変える必要もないのでいいですよ(⌒∇⌒)
③料金・追加費用の有無


ショップを決める際、ライセンス取得の料金は必ず確認しますよね。
その時に、料金だけではなく内容も確認する必要があります。
ライセンスは、大体5万円~8万円で取得することができます。
安さを求めるのも大事ですが、安いにも理由があるので気をつけましょう!
逆に、高ければよいというわけでもありせん。
しっかりと、内容に見合っている料金であることを確認してからショップを決めることが大事です。
講習費に含まれていることが多い料金
- 教材費
- 講習費
- 海洋実習費
- 施設使用料
- ライセンス申請料
- 器材レンタル料
講習費に含まれていないことが多い料金
- 宿泊費
- 交通費
- 食事代
ショップによってやライセンス取得の合宿やツアーなどで組まれている場合、宿泊費なども含まれている場合があるので、上記はあくまで参考に、料金内容をしっかり確認していくださいね。



器材購入なんて、高額で結局ライセンス取るのに一番高くなりますね(笑)
④レンタル器材の状態・対応力


ライセンスを取得する際は、レンタル器材を使用します。
器材が壊れていたり、あまりにも年期が入っていて「大丈夫?」という器材は使用したくないですよね、、、
器材は、基本的に長年使用する物なので、多少色落ちしていたりはすると思います。
また、体系で使える器材のサイズが変わってきます。
器材やスーツのサイズなど、出来るだけ自分に合ったものを用意できるくらいの器材がそろっていると、レンタルでも快適にダイビングができます。
特に、BCDのサイズは少し大きいだけで、タンクが水中で左右にずれて中性浮力が取りずらかったり、泳いでるときにバランスを崩したり、、、最悪トラブルにもなりかねないので危険です。



器材の種類と対応力は結構重要!
やはり、ぴったりの自分に合ったものは購入するしかないですが、、、
⑤お客と講師の比率


大人数が苦手だったり、泳ぐことやスキルに不安があったりで、出来るだけ少人数で受けたい方もいるかもしれません。
そもそも、ライセンス取得の時、PADIでは1人のインストラクターに対して、生徒は8人までという決まりがあるので、それ以上になることはありません。
しかし、人数が多ければ多いほど周りを気にしたり、気持ちにも余裕がなく不安なままだったり、、、
そこで、ショップの特徴として、1~4人までの少人数制で講習を行っているショップがあります。
また、シーズン時期や土日祝日など世間が休みとなる日にちを避け、平日に受講することで自然と少人数で受けられることがあります。
マンツーマンは別途料金の発生があるショップがほとんどですが、少人数制を重視しているショップは結構あるので、自分に合ったスタイルで講習が受けられるショップを探してみてくださいね。



できれば、少人数制で受講できるショップをおすすめします❢
まとめ
いかがですか?
ライセンスの取得を迷っている方、スキューバ(スクーバ)ダイビングに興味がある方にとって少しでも参考になっていればうれしいです。
私自身まだまだ、初心者ダイバーで、知識や技術も薄いので、もっともっと勉強して、いろんなことをこのブログで発信できたらいいなと思っています。
また、ブログでちょくちょく使っているダイビングした時に撮った魚の写真( ´∀` )
まだまだ、へたくそでピントはあってないし、生き物たちに遊ばれている感もありますし、ライトがうまく当たっていないので色も不十分ですが、、、
これから、たくさん潜って写真や動画の技術が上がるように練習していきます(笑)
へたくそな写真でも、どんどん載せて、自分の見てきた海の世界や生き物たちをそのまま紹介していきたいからです。
また、自分の写真の技術が上がったら、振り返ったときにいい思い出にもなりますし!(^^)!
なので、「下手だなぁ」とくすっと笑って、温かく見守っていただけたら幸いです。
最後まで、読んでいただきありがとうございました。
これからもたくさん潜って、ブログの更新をしていきます。
時には、このようなライセンスや器材などについても、発信していこうと思っているので、よかったら読んでくださいね。



記念すべき、1記事目のブログ!
これから、たくさん書いていきますのでよろしくお願いします(*’ω’*)